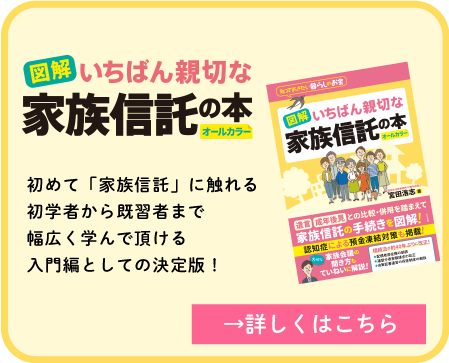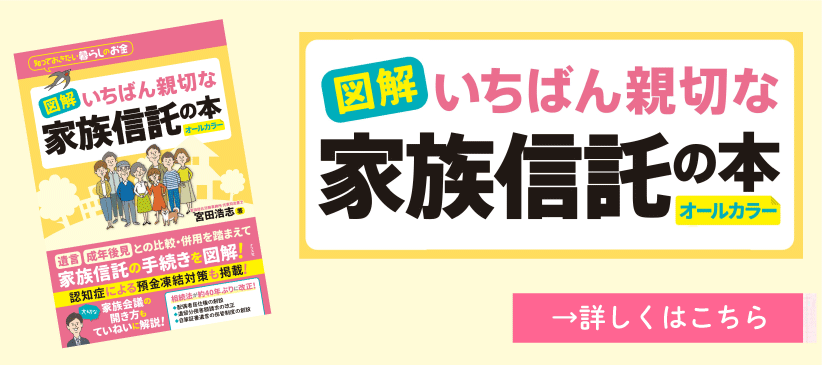中小企業のオーナー社長や創業者一族が、相続・事業承継対策として、あるいは大株主の判断能力低下による株主総会の開催不能(経営判断機能の凍結)のリスクに対する事前策として、未上場株式を信託財産として家族信託で託すケースは少なくありません。
このようなケースにおいて、信託契約書を交わす際の代表的な注意点について下記にご紹介します。
(1)指図権者
信託財産に入れた株式に関して、議決権を行使する者を誰にするかというポイントがあります。
つまり、議決権行使する権限を受託者にそのまま託すこともできますし、受託者以外の者(例えば受益者や現社長等)を「指図権者」に指定し、その者に権限を持たせることも可能です。
大株主たる創業者(現会長たる父親)が保有株式全てを信託した場合、創業者が元気なうちは父親が指図権者として引き続き議決権を行使(経営権を掌握)し、元気でなくなってきたら別の者(現社長)が議決権を行使するような設計が可能です。
(2)受託者
上記(1)のポイントに関連しますが、株式信託の受託者は、指図権者の指定が無ければ自ら議決権を行使することができる大きな権限を持ちます。
信託財産となった株式が発行済株式総数の過半数を占めている場合、実質的に受託者が経営権を掌握することにもなりかねませんので、受託者を誰にするか、また予備的に第二受託者を誰にするかというのは、非常に重要です。
(3)契約書の本数
創業者一族が複数の会社を保有するケースも多いです。
この場合、一つの信託契約で複数の会社の株式をまとめて託していいのかという問題があります。
次の(4)に関連しますが、家族信託導入の目的や今後の株式の移動(贈与・売買・相続など)の計画次第では、会社ごとに株式信託の契約を分けることも必要になるでしょう。
(4)契約信託(他益信託)か自己信託か
株式について、実質的に2次相続以降の承継者まで指定することを最大の目的としていわゆる“受益者連続型”を採用するのか、それとも相続税対策も兼ねて実質的に生前に株式を贈与しておくことを主目的にするのか、認知症による経営判断の凍結対策を主目的にするのか等により信託の設計(自己信託か契約信託か、信託の存続期間など)が異なります。
生前贈与を主目的にする場合、実質的に株式が次世代に移っていますので、委託者死亡により信託を終了させるシンプルなケースも多いです。
また、自己信託は生前贈与の仕組みとしては有効ですが、認知症対策にならないという点で注意が必要です。
(5)受益者変更権
後継者の急死や後継者としての資質の欠如、後を継ぐことを拒否等の理由により、当初計画していた後継予定者と実際の後継者が異なる緊急事態が生じることもあります。
この場合、既に後継予定者に渡してしまった株式をどのように真の後継者が回収するかという問題があります。
所有権で株式を後継予定者に渡すのではなく、株式信託における受益権で後継予定者に渡すことで、不測の事態に備えることができます。
つまり、信託契約書の中で「受益者指定権」「受益者変更権」を指定しておくことで、最後の“奥の手”として突然の後継者交代に伴い株主の地位も連動して変更できるように対策をとることができます。
(6)遺留分対策
保有資産の大半を株式が占める場合、家族間の関係性次第では遺留分対策を検討すべきケースがあります。
この場合でも株式信託が効果を発揮しますので、信託受益権に対し遺留分減殺請求がなされることを想定して対策をとることも可能です。
これまで述べましたように、株式信託についても、実は非常に論点が多く奥が深いです。
ネット上や書籍に記載された契約書のひな形に無理やり当てはめて対策をしたつもりになるのは非常に危険ですし、そのようなコンサルティングをしている専門職がいるのも事実です。
ゴーイングコンサーン(企業の永続性)を確保するためにも、創業者一族の争族を巻き起こさないためにも、的確な経営安定化策・事業承継(後継者問題)対策が求められます。
その一つの手段として、未上場株式を家族信託する手法がもっともっと選択肢として検討され、実際に有効活用されていくことを望みますし、弊所がその一助になれれば幸いです。